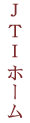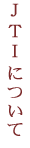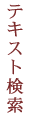構内にある礼拝堂から、日曜日の朝礼を知らせる鐘の音が響いて来た。風がつよいと見えて鐘は余韻なく遠くに聞える。宏子は枕の下へ手を入れて時計を見た。朝飯には出ないことにして、毛布の下でまだ睡り足りなくて熱っぽい体をのばした時、誰かが宏子の部屋のドアのすぐ外のところへくっついて、
「ね、そんなに云わないで――一人で行って頂戴よ。私の勝手じゃないの、行ったって行かなくったって」
初めは哀願するように、しまいには憤ったように飾りっ気のないふくれた調子で云っている。秋田訛のある杉登誉子の声であった。
「ですけれどね、きのうイー・エス・エスのときミス・ソーヤーがあなたのことをわざわざきいていらっしゃったんですもの。何故この頃礼拝に来なくなったのかって――私仕方がないから、アイ・ドント・ノウって云ったわ。そしたらミス・ソーヤーは、シイ・イズ・ア・ナイスガアルっておっしゃったんですもの……行きましょうよ!」
困ったように杉は黙りこんでいたが、
「あたし、ちっともナイスガアルなんかじゃないわ」
内気な中に譲歩しない口調で、やっぱり秋田訛を響かせてねばっている。宏子は、枕の上に片肱ついて半身起き上りながら、この不器用でいて、しかもこういう学校生活の間では相当な意味をもっている問答に聞耳を立てた。杉が断り切れるか、どうか心配のようでもあった。杉は地方のミッション・スクウルからの習慣でずっと礼拝に出ていたのだが、三週間ばかり前からそれをやめた。戦旗の読者になったばかりなのであった。
礼拝に行くことをすすめているのは、宏子たちの級の幹事をやっていて英語会話会員の飯田満子の声であった。
「ここにいる以上ミス・ソーヤーに睨まれたら損よ。たった四十分じゃありませんか」
「……だから、あなた早く行っていらっしゃいって云うのに――」
「私またきかれたら何て返事したらいいの? あなたの行かない理由さえきかして呉れれば私一人でだって行くわ」
短い沈黙の後、戸のこっち側で聞いていてさえその瞬間杉の小じんまりした顔がパッと赧らんだのがわかるような調子で云った。
「あたし、あんな礼拝、ちっとも霊感がないから厭になっちゃったの。わかった? わかったら行ってよ」
「――困ったひとねえ」
霊感という、よく説教の中にくりかえされるつかまえどころのない一言が逆な功を奏して、飯田は悄気たような呟きをのこして行ってしまった。枕の上へ頭をおとして天井を眺めながら聴いていた宏子の口元がおかしそうにゆるんだ。
形式的にノックして、ドアが勢よく開いた。
「聞いた?」
杉が、目鼻だちのちんまりとした善良な顔に、自分の思いつきが成功したのさえいやだ、という表情を泛べて宏子の寝台の横へ来た。
「何てうるさいんでしょう、ひとのことまで」
「大変うまく行ったじゃないの」
「そうかしら」
笑いもせず杉は、
「でも、内心きっとやっきなのよ。この頃随分出ない人が殖えたんですもの。正面から出なさいって云えないもんだから――いやねえ、飯田さんなんか使って」
若い娘たちの或る時代の気分から聖書や礼拝に何となし感傷的な気分を牽きつけられていた学生の中にも、左翼の思想は浸潤して行って、目に見えず急速な分裂をひき起しているのであった。
「そう云えば」
大きくはないがくっきりとした二重瞼の眼を見張るようにして杉が、
「あなたどっか工合がわるいの?」
ときいた。
「どうして?」
「食堂で沖がカキに何か云ってたから――」
宏子は、黙ったまま肩をすくめた。
「本当はきのう泊るつもりで家へ行ったんだけれど、急に帰って来ちゃったもんだから」
「ふーん」
一晩睡って眼を醒した今でも、宏子の心の中には家での印象が一杯に、重く複雑にのこされている。杉は真率で勝気なところもある可愛い娘であるが、その天性は、こうして相対している宏子がそんなこと迄うちあけたいと思うだけの何かの力を欠いているのであった。
起き出して宏子は寝台を整え始めた。それをよけて窓を背にして靠れながら杉は、
「あたし今日兄さんのところへ行こうかと思ってたんだけれど、やめよう」
気落ちしたように云った。
「どうして?」
「つまんないんですもの――お洗濯ばっかりしてやって帰って来るなんて。――それでも少しはよろこんで呉れるんならいいけれど、まるで当然みたいな顔をしてるんだもの」
杉の家は故郷で代々医者であった。後継ぎの兄はアパート住居で慈恵に通っていた。
「どうしてあんな謡曲なんか好きなんでしょう。若い癖して、ねえ。全くくさくさしちゃうわ、あたし……」
杉と宏子は連立って部屋を出た。半分開けっぱなしになっているドアの隙間から、明るい室内の空気が照るように派手な友禅の羽織の後姿が見えたり、階段の中途で一人は上に一人は下に立ち止って顔を向けあって何か喋っている、両方ともが広幅帯をきっちり胸のところにしめていたり。ふだん主に洋服で暮しているここの学生は日曜日には半数以上着物になって、新しい足袋や袂をぎごちなさが珍しくうれしそうに、ざわめいているのであった。
洗面所のところで予科の学生が、ふだん畳んでしまわれてばかりいるのできっちり折目の立った銘仙の長い二つの袂を肩の上へ掬いあげて、
「あらあ、いやだわ、私。本当に大丈夫かしら、盲腸になんないかしら。――いやだわあ」
としきりに水をのんでいる。間違えて果物の種をのんだのである。
社交室では、祇園小唄のようなレコードが鳴っていて、それに合わせて女同士六組ばかりがダンスをしている。
一歩外へ出れば、晩秋の畑と雑木林とが地平線まで広闊に拡っていて、あたりには町並もなかったから、日曜日の午後の女学生たちのこういうとりとめない色彩の溢れたざわめきは、周囲と切りはなされて、無形の柵の中に囲われている一団のような感じを与えるのであった。
奥庭の、ヒマラヤ杉のかげにある日だまりのベンチのところで演劇部のものがクリスマスにやる英語芝居の科白を諳誦していた。
「おお! マリア! 見たか? お前は確に見たか?」
一つの声が英語でそう問いつめよった。すると、その答えをするべきマリアが突然日本語になって、声を落しながらも十分聞きとれるように特別に抑揚をつけて、
「ええ見ましてすとも」
と答えた。
「上海へ着きますとねえ、マア支那人ばっかりいたんでございますよ」
シーッ! 圧えても圧えても鎮まることの出来ない生気溢れる笑いが続いた。カキ、即ち柿内ナミという生徒監が先頃上海視察に行って、帰った時講堂に学生を集めて報告をした。その第一声がこの近頃の傑作である上海へ着きますとねえ、なのであった。
お八つの時間に、日曜日らしくお汁粉が出された。食堂を出て、今日は店番をしている人のいない購買組合の店のところへ来かかった時、
「ちょっと! ちょっとってば!」
はる子がうしろから小走りにかけて来て、宏子の肩をつかまえた。
「知ってる? 三田先生やめさせられるらしいのよ」
「ほんと?」
折からその食堂からの大廊下をぞろぞろと通りがかっていた学生たちが、
「三田先生がどうしたって?」
「なんなの」
「どこできいたの?」
ぐるりと集って来てはる子のまわりを取巻いた。