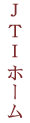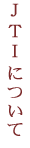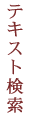「――(この上誰か、この手毬の持主に逢えるとなれば、爺さん、私は本望だ、野山に起臥して旅をするのもそのためだ。)
と、話さっしゃるでの。村を賞められたが憎くねえだし、またそれまでに思わっしゃるものを、ただわかりましねえで放擲しては、何か私、気が済まねえ。
そこで、草原へ蹲み込んで、信にはなさりますめえけんど、と嘉吉に蒼い珠授けさしった……」
しばらく黙って、
「の、事を話したらばの。先生様の前だけんど、嘘を吐け、と天窓からけなさっしゃりそうな少え方が、
(おお、その珠と見えたのも、大方星ほどの手毬だろう。)と、あのまた碧い星を視めて云うだ。けちりんも疑わねえ。
(なら、まだ話します事がござります、)とついでに黒門の空邸の話をするとの。
(川はその邸の、庭か背戸を通って流れはしないか。)
と乗出しけよ。……(流れは見さっしゃる通りだ)……」
今もおなじような風情である。――薄りと廂を包む小家の、紫の煙の中も繞れば、低く裏山の根にかかった、一刷灰色の靄の間も通る。青田の高低、麓の凸凹に従うて、柔かにのんどりした、この一巻の布は、朝霞には白地の手拭、夕焼には茜の襟、襷になり帯になり、果は薄の裳になって、今もある通り、村はずれの谷戸口を、明神の下あたりから次第に子産石の浜に消えて、どこへ灌ぐということもない。口につけると塩気があるから、海潮がさすのであろう。その川裾のたよりなく草に隠れるにつけて、明神の手水洗にかけた献燈の発句には、これを霞川、と書いてあるが、俗に呼んで湯川と云う。
霞に紛れ、靄に交って、ほのぼのと白く、いつも水気の立つ処から、言い習わしたものらしい。
あの、薄煙、あの、靄の、一際夕暮を染めたかなたこなたは、遠方の松の梢も、近間なる柳の根も、いずれもこの水の淀んだ処で。畑一つ前途を仕切って、縦に幅広く水気が立って、小高い礎を朦朧と上に浮かしたのは、森の下闇で、靄が余所よりも判然と濃くかかったせいで、鶴谷が別宅のその黒門の一構。
三人は、彼処をさして辿るのである。
ここに渠等が伝う岸は、一間ばかりの川幅であるが、鶴谷の本宅の辺では、およそ三間に拡がって、川裾は早やその辺からびしょびしょと草に隠れる。
ここへは、流をさかのぼって来るので、間には橋一つ渡らねばならぬ。
橋は明神の前へ、三崎街道に一つ、村の中に一つ。今しがた渠等が渡って、ここから見えるその村の橋も、鶴谷の手で欄干はついているが、細流の水静かなれば、偏に風情を添えたよう。青い山から靄の麓へ架け渡したようにも見え、低い堤防の、茅屋から茅屋の軒へ、階子を横えたようにも見え、とある大家の、物好に、長く渡した廻廊かとも視められる。
灯もやや、ちらちらと青田に透く。川下の其方は、藁屋続きに、海が映って空も明い。――水上の奥になるほど、樹の枝に、茅葺の屋根が掛って、蓑虫が塒したような小家がちの、それも三つが二つ、やがて一つ、窓の明も射さず、水を離れた夕炊の煙ばかり、細く沖で救を呼ぶ白旗のように、風のまにまに打靡く。海の方は、暮が遅くて灯が疾く、山の裾は、暮が早くて、燈が遅いそうな。
まだそれも、鳴子引けば遠近に便があろう。家と家とが間を隔て、岸を措いても相望むのに、黒門の別邸は、かけ離れた森の中に、ただ孤家の、四方へ大なる蜘蛛のごとく脚を拡げて、どこまでもその暗い影を畝らせる。
月は、その上にかかっているのに。……
先達の仁右衛門は、早やその樹立の、余波の夜に肩を入れた。が、見た目のさしわたしに似ない、帯がたるんだ、ゆるやかな川添の道は、本宅から約八丁というのである。
宰八が言続いで、
「……(外廻りを流れて来るし、何もハイ空家から手毬を落す筈はねえ。そんでも猫の死骸なら、あすこへ持って行って打棄った奴があるかも知んねえ、草ぼうぼうだでのう、)と私、話をしただがね。」