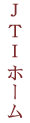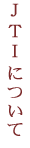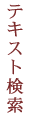その夜に限って何事もなく、静かに。……寝ようという時、初夜過ぎた。
宰八が手燭に送られて、広縁を折曲って、遥かに廻廊を通った僧は、雨戸の並木を越えたようで、故郷には蚊帳を釣って、一人寂しく友が待つ思がある。
「ここかい。」
「それを左へ開けさっせえまし、入口の板敷から二ツ目のが、男が立って遣るのでがす。行抜けに北の縁側へも出られますで、お前様帰りがけに取違えてはなんねえだよ。
二三年この方、向うへは誰も通抜けた事がねえで、当節柄じゃ、迷込んではどこへ行くか、ハイ方角が着きましねえ。」
「もう分りましたよ。」
「可かあねえ、私、ここに待っとるで、燈をたよりに出て来さっせえ。
私も、この障子の多いこと続いたのに、めらめら破れのある工合が、ハイ一ツ一ツ白髑髏のようで、一人で立ってる気はしねえけんど、お前様が坊様だけに気丈夫だ。えら茶話がもてて、何度も土瓶をかわかしたで、入かわって私もやらかしますべいに、待ってるだよ。」
僧は戸を開けながら、と、声をかけて、
「御免下さい。」
と、ぴたりと閉めた。
「あ、あ、気味の悪い。誰に挨拶さっせるだ。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。はて、急に変なことを[15]考えだぞ。そこさ一面の障子の破れ覗いたら何が見えべい――南無阿弥陀仏、ああ、南無阿弥陀仏、……やあ、蝋燭がひらひらする、どこから風が吹いて来るだ。これえ消したが最後、立処に六道の辻に迷うだて。南無阿弥陀仏、御坊様、まだかね。」
「ちょいと、」
「ひゃあ、」
僧は半ば開いて、中に鼠の法衣で立ちつつ、
「ちょいと燭を見せておくれ。」
「ええ、お前様、前へ戸を開けておいてから何か言わっしゃれば可い。板戸が音声を発したか、と吃驚しただ、はあ、何だね。」
「入口の、この出窓の下に、手水鉢があったのを、入りしなに見ておいたが、広いので暗くて分らなくなりました。」
「ああ、手、洗わっしゃるのかね、」
と手燭ばかりを、ずいと出して、
「鉢前にゃ、夜が明けたら見さっせえまし、大した唐銅の手水鉢の、この邸さ曳いて来る時分に牛一頭かかった、見事なのがあるけんど、今開ける気はしましねえ。……」
ええ、そよら、そよらと風だ。
そ、その鉢にゃ水があれば可いがね、無くば座敷まで我慢さっせえまし、土瓶の残を注けて進ぜる。」
「あります、あります。」
ざっと音をさして、
「冷い美しい水が、満々とありますよ。」
「嘘を吐くもんでェねえ。なに美い水があんべい。井戸の水は真蒼で、小川の水は白濁りだ。」
「じゃあ燭で見るせいだろうか、」
「そして、はあ、何なみなみとあるもんだ。」
「いいえ、縁切こぼれるようだよ。ああ、葉越さんは綺麗好きだと見える。真白な手拭が、」
と言いかけてしばらく黙った。
今年より卯月八日は吉日よ
尾長蛆虫成敗ぞする
「ここに倒にはってあるのは、これは誰方がお書きなすった、」
「……南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏……」
「ああ、佳いおてだ。」
と大和尚のように落着いて、大く言ったが、やがてちと慌しげに小さな坊さまになって急いで出た。
「ええ、疾く出さっせえ、私もう押堪えて、座敷から庭へ出て用たすべい。」
「ほんとに誰が書いたんだね、女の手だが、」
と掛手拭を賞めた癖に、薄汚れた畳んだのを自分の袂から出している。
「南無阿弥陀仏、ソ、それは、それ、この次の、次の、小座敷で亡くならしっけえ、どっかの嬢様が書いて貼っただとよ、直きそこだ、今ソンな事あどうでも可え。頭から、慄然とするだに、」
「そうかい、ああ私も今、手を拭こうとすると、真新しい切立の掛手拭が、冷く濡れていたのでヒヤリとした。」
「や、」と横飛びにどたりと踏んだが、その跫音を忍びたそうに、腰を浮かせて、同一処を蹌踉蹌踉する。