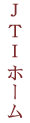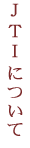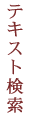一門の采邑、六十餘州の半を越え、公卿・殿上人三十餘人、諸司衞府を合せて門下郎黨の大官榮職を恣にするもの其の數を知らず、げに平家の世は今を盛りとぞ見えにける。新大納言が隱謀脆くも敗れて、身は西海の隅に死し、丹波の少將成經、平判官康頼、法勝寺の執事俊寛等、徒黨の面々、波路遙かに名も恐ろしき鬼界が島に流されしより、世は愈々平家の勢ひに麟伏し、道路目を側つれども背後に指す人だになし。一國の生殺與奪の權は、入道が眉目の間に在りて、衞府判官は其の爪牙たるに過ぎず。苟も身一門の末葉に連れば、公卿華胄の公達も敢えて肩を竝ぶる者なく、前代未聞の榮華は、天下の耳目を驚かせり。されば日に増し募る入道が無道の行爲、一朝の怒に其の身を忘れ、小松内府の諫をも用ひず、恐れ多くも後白河法皇を鳥羽の北殿に押籠め奉り、卿相雲客の或は累代の官職を褫れ、或は遠島に流人となるもの四十餘人。鄙も都も怨嗟の聲に充ち、天下の望み既に離れて、衰亡の兆漸く現はれんとすれども、今日の歡びに明日の哀れを想ふ人もなし。盛者必衰の理とは謂ひながら、權門の末路、中々に言葉にも盡されね。父入道が非道の擧動は一次再三の苦諫にも及ばれず、君父の間に立ちて忠孝二道に一身の兩全を期し難く、驕る平家の行末を浮べる雲と頼みなく、思ひ積りて熟々世の無常を感じたる小松の内大臣重盛卿、先頃思ふ旨ありて、熊野參籠の事ありしが、歸洛の後は一室に閉籠りて、猥りに人に面を合はせ給はず、外には所勞と披露ありて出仕もなし。然れば平生徳に懷き恩に浴せる者は言ふも更なり、知るも知らぬも潛かに憂ひ傷まざるはなかりけり。
* *
* *
短き秋の日影もやゝ西に傾きて、風の音さへ澄み渡るはづき半の夕暮の空、前には閑庭を控へて左右は廻廊[10]を繞らし、青海の簾長く垂れこめて、微月の銀鈎空しく懸れる一室は、小松殿が居間なり。内には寂然として人なきが如く、只々簾を漏れて心細くも立迷ふ香煙一縷、をりをりかすかに聞ゆる戞々の音は、念珠を爪繰る響にや、主が消息を齎らして、いと奧床し。
やゝありて『誰かある』と呼ぶ聲す、那方なる廊下の妻戸を開けて徐ろに出で來りたる立烏帽子に布衣着たる侍は齋藤瀧口なり。『時頼參りて候』と申上ぐれば、やがて一間を出で立ち給ふ小松殿、身には山藍色の形木を摺りたる白布の服を纏ひ、手には水晶の珠數を掛け、ありしにも似ず窶れ給ひし御顏に笑を含み、『珍らしや瀧口、此程より病氣の由にて予が熊野參籠の折より見えざりしが、僅の間に痛く痩せ衰へし其方が顏容、日頃鬼とも組まんず勇士も身内の敵には勝たれぬよな、病は癒えしか』。瀧口はやゝしばし、詰と御顏を見上げ居たりしが、『久しく御前に遠りたれば、餘りの御懷しさに病餘の身をも顧みず、先刻遠侍に伺候致せしが、幸にして御拜顏の折を得て、時頼身にとりて恐悦の至りに候』。言ふと其儘御前に打ち伏し、濡羽の鬢に小波を打たせて悲愁の樣子、徒ならず見えけり。
哀れや瀧口、世を捨てん身にも今を限りの名殘には一切の諸縁何れか煩惱ならぬはなし。比世の思ひ出に、夫とはなしに餘所ながらの告別とは神ならぬ身の知り給はぬ小松殿、瀧口が平生の快濶なるに似もやらで、打ち萎れたる容姿を、訝しげに見やり給ふぞ理なる。
四方山の物語に時移り、入日の影も何時しか消えて、冴え渡る空に星影寒く、階下の叢に蟲の鳴く聲露ほしげなり。燭を運び來りし水干に緋の袴着けたる童の後影見送りて、小松殿は聲を忍ばせ、『時頼、近う寄れ、得難き折なれば、予が改めて其方に頼み置く事あり』。