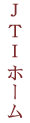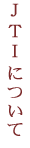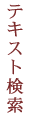一の三
「やあ、くたびれた、くたびれた」
足袋草鞋脱ぎすてて、出迎う二人にちょっと会釈しながら、廊下に上りて来し二十三四の洋服の男、提燈持ちし若い者を見返りて、
「いや、御苦労、御苦労。その花は、面倒だが、湯につけて置いてもらおうか」
「まあ、きれい!」
「本当にま、きれいな躑躅でございますこと! 旦那様、どちらでお採り遊ばしました?」
「きれいだろう。そら、黄色いやつもある。葉が石楠に似とるだろう。明朝浪さんに活けてもらおうと思って、折って来たんだ。……どれ、すぐ湯に入って来ようか」
*
「本当に旦那様はお活発でいらっしゃいますこと! どうしても軍人のお方様はお違い遊ばしますねエ、奥様」
奥様は丁寧に畳みし外套をそっと接吻して衣桁にかけつつ、ただほほえみて無言なり。
階段も轟と上る足音障子の外に絶えて、「ああいい心地!」と入り来る先刻の壮夫。
「おや、旦那様もうお上がり遊ばして?」
「男だもの。あはははは」と快く笑いながら、妻がきまりわるげに被る大縞の褞袍引きかけて、「失敬」と座ぶとんの上にあぐらをかき、両手に頬をなでぬ。栗虫のように肥えし五分刈り頭の、日にやけし顔はさながら熟せる桃のごとく、眉濃く目いきいきと、鼻下にうっすり毛虫ほどの髭は見えながら、まだどこやらに幼な顔の残りて、ほほえまるべき男なり。
「あなた、お手紙が」
「あ、乃舅だな」
壮夫はちょいといずまいを直して、封を切り、なかを出せば落つる別封。
「これは浪さんのだ――ふむ、お変わりもないと見える……はははは滑稽をおっしゃるな……お話を聞くようだ」笑を含んで読み終えし手紙を巻いてそばに置く。
「おまえにもよろしく。場所が変わるから、持病の起こらぬように用心おしっておっしゃってよ」と「浪さん」は饌を運べる老女を顧みつ。
「まあ、さようでございますか、ありがとう存じます」
「さあ、飯だ、飯だ、今日は握り飯二つで終日歩きずめだったから、腹が減ったこったらおびただしい。……ははは。こらあ何ちゅう魚だな、鮎でもなしと……」
「山女とか申しましたっけ――ねエばあや」
「そう? うまい、なかなかうまい、それお代わりだ」
「ほほほ、旦那様のお早うございますこと」
「そのはずさ。今日は榛名から相馬が嶽に上って、それから二ツ嶽に上って、屏風岩の下まで来ると迎えの者に会ったんだ」
「そんなにお歩き遊ばしたの?」
「しかし相馬が嶽のながめはよかったよ。浪さんに見せたいくらいだ。一方は茫々たる平原さ、利根がはるかに流れてね。一方はいわゆる山また山さ、その上から富士がちょっぽりのぞいてるなんぞはすこぶる妙だ。歌でも詠めたら、ひとつ人麿と腕っ比べをしてやるところだった。あはははは。そらもひとつお代わりだ」
「そんなに景色がようございますの。行って見とうございましたこと!」
「ふふふふ。浪さんが上れたら、金鵄勲章をあげるよ。そらあ急嶮い山だ、鉄鎖が十本もさがってるのを、つたって上るのだからね。僕なんざ江田島で鍛い上げたからだで、今でもすわというとマストでも綱でもぶら下がる男だから、何でもないがね、浪さんなんざ東京の土踏んだ事もあるまい」
「まあ、あんな事を」にっこり顔をあからめ「これでも学校では体操もいたしましたし――」
「ふふふふ。華族女学校の体操じゃ仕方がない。そうそう、いつだっけ、参観に行ったら、琴だか何だかコロンコロン鳴ってて、一方で『地球の上に国という国は』何とか歌うと、女生が扇を持って起ったりしゃがんだりぐるり回ったりしとるから、踊りの温習かと思ったら、あれが体操さ! あはははは」
「まあ、お口がお悪い!」
「そうそう。あの時山木の女と並んで、垂髪に結って、ありあ何とか言ったっけ、葡萄色の袴はいて澄ましておどってたのは、たしか浪さんだっけ」
「ほほほほ、あんな言を! あの山木さんをご存じでいらっしゃいますの?」
「山木はね、うちの亡父が世話したんで、今に出入りしとるのさ。はははは、浪さんが敗北したもんだから黙ってしまったね」
「あんな言!」
「おほほほほ。そんなに御夫婦げんかを遊ばしちゃいけません。さ、さ、お仲直りのお茶でございますよ。ほほほほ」